心がなんだか落ち着かない、いつもよりもイライラしてしまう。
そんな不安やストレスを抱えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、ちょっとした心の不調に選ばれることのある和漢処方を5つ紹介します。
また、登録販売者の視点からメンタルケアに和漢処方を活かす選び方についても解説していきます。
本記事は、登録販売者資格を持ち、一般用医薬品に関する情報発信を行なっている筆者が、信頼できる公的情報に基づいて執筆しています。
※記事内容はあくまで一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療を意図するものではありません。
双極症の当事者である側面から、実際の体験を踏まえ、心のバランスを保つ方法も発信しています。
※本記事で紹介している心のバランスを保つ方法は、筆者自身の体験に基づくものであり、必ずしもすべての方に効果があるとは限りません。
体質・考え方・生活環境などにより、感じ方や効果には個人差が生じます。
ご自身に合った方法を無理のない範囲で取り入れてみてください。
和漢処方の考え方とは?
和漢処方は、西洋医学とは異なった「東洋医学」を基にして、いくつかの生薬成分を掛け合わせたものです。
ここでは、東洋医学の特徴について解説していきます。
東洋医学独自の病態認識「証」
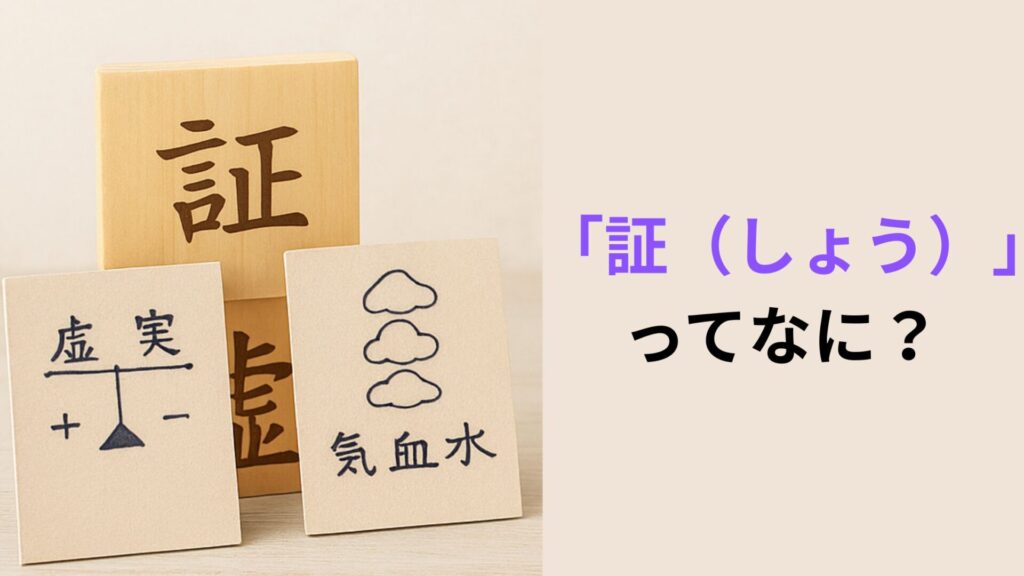
東洋医学の特徴として、西洋医学にはない「証(しょう)」と呼ばれる病態認識が存在します。
「虚実」・「陰陽」・「気血水」「五臓」などに分類されるのが「証」です。
しかし、一般的に、一般用医薬品における和漢処方では「証」という言葉は使われません。
一般用医薬品での「証」にあたる言葉は、「しばり」(使用制限)とされています。
「証」と「しばり」の関係
| 証 | しばり | |
| 虚実 | 実の病態 | 体力が充実 |
| 虚実の尺度で中間の病態 | 体力中等度 | |
| 虚の病態 | 体力虚弱 | |
| 虚実の病態に関わらず幅広く | 体力に関わらず | |
| 陰陽 | 陽の病態 | のぼせぎみで顔色が赤く |
| 陰の病態 | 疲れやすく冷えやすい | |
| 気血水 | 水毒の病態 | 口渇があり、尿量が減少する |
| 血虚の病態 | 皮膚の色艶が悪く | |
| 五臓 | 脾胃虚弱(ひいきょじゃく)の病態 | 胃腸虚弱 |
| 肝陽上亢(かんようじょうこう)の病態(肝の失調状態) | イライラして落ち着きのない | |
表にある「しばり」に基づいて、体力や体質・症状から和漢素材を選択するのが基本です。
東洋医学を「中国のもの」だと勘違いしてしまう人がいるかもしれません。
しかし、東洋医学は日本で発展した「日本」の伝統医学です。
和漢処方は、独自の病態認識である「証」=「しばり」(一般用医薬品の場合)に合わせて、選択されるようになっています。

自分の「証」に合った和漢成分を知ることが選択のヒントなんですね



自己判断ではなく、医師・薬剤師・登録販売者に状態を伝えて選択しましょう
「心身一如」という考え方


東洋医学の考え方には「心身一如(しんしんいちにょ)」があります。
「心身一如」とは、「心の不調が体の不調につながる」・「体の不調は心の不調につながる」という考え方です。
和漢素材は心身の状態を総合的にとらえるアプローチとして親しまれてきました。
「心と体が密接に関係している」のは、なんとなくイメージがつきやすいのではないでしょうか。



「心身一如」が東洋医学の基本的な考え方なんですね!



心と体のゆらぎに着目しているのが和漢素材です
心の不調に選ばれる和漢処方5選
心身の状態を総合的にとらえるアプローチとして親しまれている和漢処方。
ここからは、心の不調に選ばれることのある和漢処方を5つ紹介していきます。
①加味逍遙散(かみしょうようさん)


心の不調で使われることがある和漢処方の1つ目は「加味逍遙散」です。
加味逍遙散の「しばり」は、体力中等度以下とされています。
加味逍遙散は、主に以下のような場合に用いられることが多いです。
- イライラしやすく、情緒不安定になりやすい人
- 冷えを感じやすい女性
- PMS(月経前症候群)や更年期のサポート
重篤な副作用として、「肝機能障害」「腸管膜静脈硬化症」がみられる場合があります。
胃腸の弱い人の場合は、吐き気・嘔吐・胃部不快感・下痢なども起きやすいので注意が必要です



PMSでのイライラ感に選択する人も多いんですね



副作用が出る場合もあるので、医師・薬剤師、登録販売者への相談は必ずしてくださいね
②抑肝散(よくかんさん)
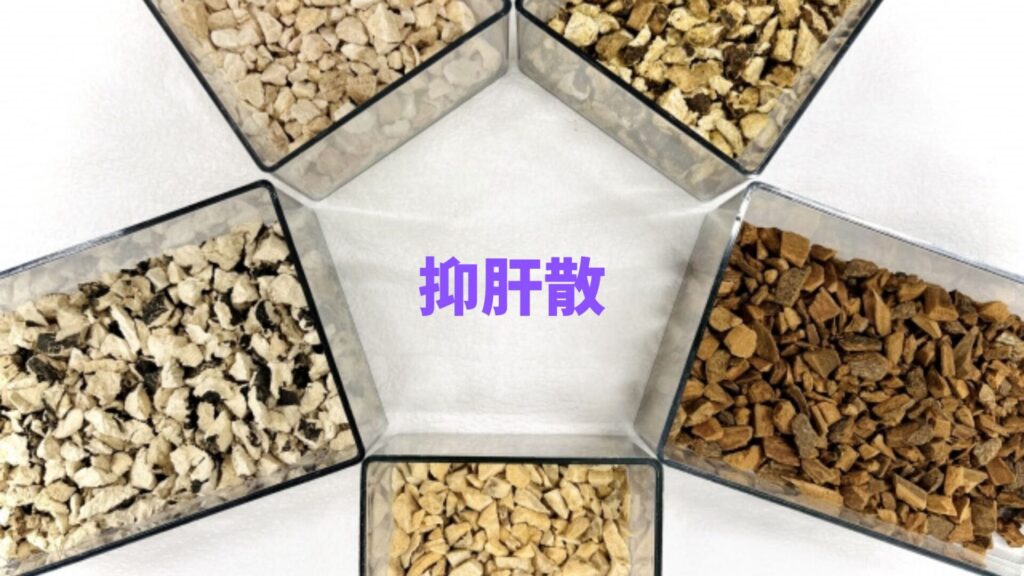
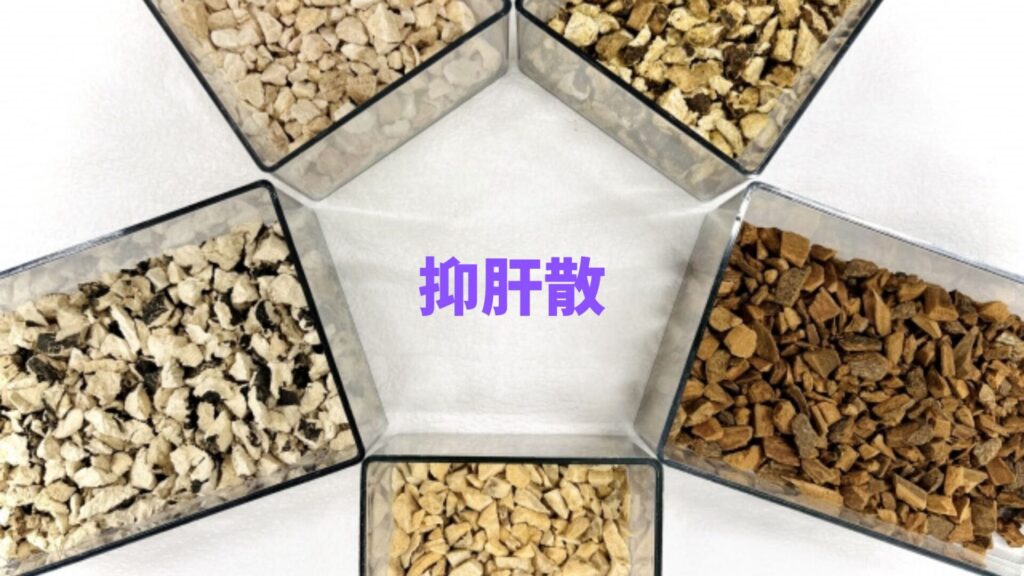
心の不調に用いられることがある和漢処方の2つ目は「抑肝散」です。
抑肝散の「しばり」は、体力中等度を目安として幅広く用いられることがあります。
抑肝散が用いられるのは、以下のような場合です。
- 神経が高ぶりやすく、怒りやすい人
- 不眠傾向にある人
- 更年期障害
次のような症状が出た場合は、直ちに医療機関を受診してください
- 動くと息が苦しい
- 急に体重が増えた→心不全を引き起こす可能性があります



抑肝散は、幅広く使われることがある和漢処方なんですね



体質や症状による個人差はあるので、医師・薬剤師、登録販売者への相談は忘れずに!
③柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)


心の不調時に選ばれることがある和漢処方の3つ目は「柴胡加竜骨牡蛎湯」です。
柴胡加竜骨牡蛎湯の「しばり」は、体力中等度以上とされています。
柴胡加竜骨牡蛎湯が用いられるのは、主に以下の場合です。
- 精神的な不安があり、動悸や不眠がある人
- 高血圧の随伴症状による動悸、不眠、不安
以下のような人は、腹痛や下痢などの副作用が現れやすいので、注意してください。
- 体力虚弱な人
- 胃腸が弱く下痢をしやすい人
- 下剤を服用している人
また、重篤な副作用として、「肝機能障害」や「間質性肺炎」もあります。



胃腸が弱い人には不向きなんですね



重篤な副作用が生じる場合もあるので、医師・薬剤師、登録販売者に相談を欠かさずに!
④桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)


心が不調なときに使用されることがある和漢処方の4つ目は「桂枝加竜骨牡蛎湯」です。
桂枝加竜骨牡蛎湯の「しばり」は、体力中等度以下とされています。
桂枝加竜骨牡蛎湯が選ばれるのは、主に以下のような場合です。
- 疲れやすく、興奮しやすい人
- 不眠症
- 神経症



精神不安や不眠に用いられることが多いんですね



重篤な副作用は報告されていないけど、必ず医師、薬剤師・登録販売者に相談してくださいね
⑤半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)


心の不調時に選択されることが多い5つ目の和漢処方は「半夏厚朴湯」です。
半夏厚朴湯の「しばり」は、体力中等度を目安として幅広く応用されています。
半夏厚朴湯が使われることが多いのは、以下のような場合です。
- 気分がふさいでしまう人
- 咽喉・食道部に異物感がある人
- ときに動悸やめまいなどを感じる不安神経症
半夏厚朴湯は、心の不調時に選ばれるだけでなく、かぜの諸症状が現れた際にも選ばれることがあります。
比較的副作用が少ないとされていますが、使用前に医師、薬剤師・登録販売者への相談は必ずおこないましょう。



緊張によって、喉のつかえ感やめまいを感じる人もいますよね



そうですね。緊張による不安に選ばれることも多いですよ
和漢処方をメンタルケアに活かす選び方
心に不調で選ばれる和漢処方について、いくつか紹介しました。
実際のメンタルケアに和漢処方を活かすためには、どのような選び方をすればいいのか知りたい人も多いかもしれません。
ここからは、メンタルケアに選ばれる和漢処方を症状別に活かす選び方を紹介していきます。
イライラや不安感が強い場合


イライラや不安感が強く出てしまう人の場合、以下のような和漢処方を選ぶ人が多いです。
イライラや不安感が強く現れている場合に使用されやすい和漢処方
- 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 抑肝散
- 加味逍遙散
これまで紹介した和漢処方の中では、上記3つが選択肢として挙がることがあります。
そのほかには、「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」も選択されやすいです。
「抑肝散加陳皮半夏」の情報
- 「しばり」は、体力中等度を目安
- やや消化器が弱い人に、幅広く使用されることが多い
- 「抑肝散」に「陳皮(ミカン科のウンシュウミカンの果皮)」を加えている
- 陳皮の作用として、香りによる健胃が含まれている



消化器が弱い人は「抑肝散加陳皮半夏」の使用が向いているのですね



選択されやすいですが、医師や薬剤師・登録販売者への相談はしましょうね!
不眠に悩んでいる場合


メンタルの不調で、日頃から不眠に悩んでいる場合には、以下のような和漢処方が用いられることがあります。
精神的な不調で不眠に悩んでいる場合に選択されやすい和漢処方
- 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 抑肝散
これまで紹介した中で、特に頻繁に選ばれるのは、上記の3つです。
そのほかにも「加味帰脾湯(かみきひとう)」や「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」も選ばれます。
「加味帰脾湯」の情報
- 「しばり」は、体力中等度以下
- 心身の疲れがあり、血色が悪い人に使われやすい
「酸棗仁湯」の情報
- 「しばり」は、体力中等度以下
- 心身が疲れている人に使われやすい
- 胃腸が弱い人、下痢または下痢傾向のある人は、消化器系の副作用が現れやすい



メンタルの不調から不眠の症状が現れる人も少なくないですよね



不眠は和漢処方だけでは改善しないことがあるので、早めに医師に相談するのが大切です
心だけではなく、身体にも症状がある場合


心の不調により、身体にも症状が出るという人も少なくないでしょう。
心だけではなく、身体にも症状がある場合には、次のような和漢処方が選択肢となることがあります。
心の不調から身体の不調を感じてしまう人が選ぶことが多い和漢処方
- 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 加味逍遙散
- 加味帰脾湯
- 酸棗仁湯



これまでに紹介した和漢処方が選択されるケースが多いのですね



医師・薬剤師、登録販売者に自分の体質を相談するのを忘れずに!
和漢処方を服用する際のポイント
心の不調に選ばれる和漢処方を紹介してきましたが、服用する際のポイントがいくつかあります。
ここからは、和漢処方の服用におけるポイントを押さえていきましょう。
和漢処方を服用するタイミング


心の不調を感じたとき、和漢処方を服用するタイミングも確認しておきましょう。
和漢処方を服用するタイミング
- 基本的には「食前」または「食間(食事と食事の間)」に服用
- 胃腸の弱い人は、「食後」に服用することで、胃への負担が軽くなる場合がある
和漢処方は、胃のなかに何も入っていない状態で服用するのが良いとされています。
理由としては、何も入っていない胃の場合、有効成分の吸収がスムーズになるといわれているためです。
和漢処方を服用するたタイミングは、基本的に「食前」または「食間」にしましょう。
しかし、胃腸が弱い人は、有効成分の効き目が強く出る場合もあります。
その場合は、「食後」の服用で胃への刺激を緩和できるとされています。



食前または食間の服用で、吸収が促進されることがあるのですね!



胃腸への負担が気になる人は、事前に医師・薬剤師、登録販売者へ伝えましょう
和漢処方を服用する際の注意点


和漢処方を服用する際の注意点もいくつか紹介していきます。
和漢処方を服用する際に気を付けるポイント
- ぬるま湯または水で服用する(緑茶やコーヒーは避ける)
- アルコールとの同時摂取は避ける
- 他の医薬品との併用は、医師や薬剤師、登録販売者に相談する
和漢処方を服用する場合は、「ぬるま湯」か「水」が一般的です。
「ぬるま湯」や「水」で飲むことで、胃への負担が軽くなるとされています。
また、有効成分の吸収も促進させやすいです。
逆に緑茶やコーヒーの場合は、「タンニン」や「カフェイン」を含んでいるため、作用が強くなるとされています。
他にもアルコールと一緒に服用するのも避けるようにしましょう。
アルコールとの同時摂取は、作用が強まったり、副作用のリスクも高まる可能性があります。
他の医薬品を摂取している人も併用には、注意が必要です。
他の医薬品を飲んでいる場合には、事前に医師や薬剤師、登録販売者への相談を必ず行なってください。



緑茶やコーヒー、アルコールで飲まないようにします



他にも医薬品との併用にも注意しましょう
まとめ
この記事では、心の不調に選ばれる和漢処方5選を紹介しました。
また、和漢処方をメンタルケアに活かす選び方や服用する際のポイントも取り上げていきました。
記事の内容をまとめると、以下のとおりです。
- 和漢処方には「証(しょう)」という病態認識や「心身一如(しんしんいちにょ)」の考え方がある
- 「加味逍遙散」「抑肝散」「柴胡加竜骨牡蛎湯」「桂枝加竜骨牡蛎湯」「半夏厚朴湯」などが心の不調に対して選ばれる
- 和漢処方を服用するタイミングは「食前」か「食間」が望ましい
- 和漢処方は「ぬるま湯」または「水」が推奨される
- 緑茶やコーヒーでの服用やアルコールとの同意摂取は避けたほうがよい
和漢処方は体質や症状によって作用が異なるため、使用する際は必ず医師や薬剤師、登録販売者にご相談してくださいね。


日向未来
医療・健康ライター
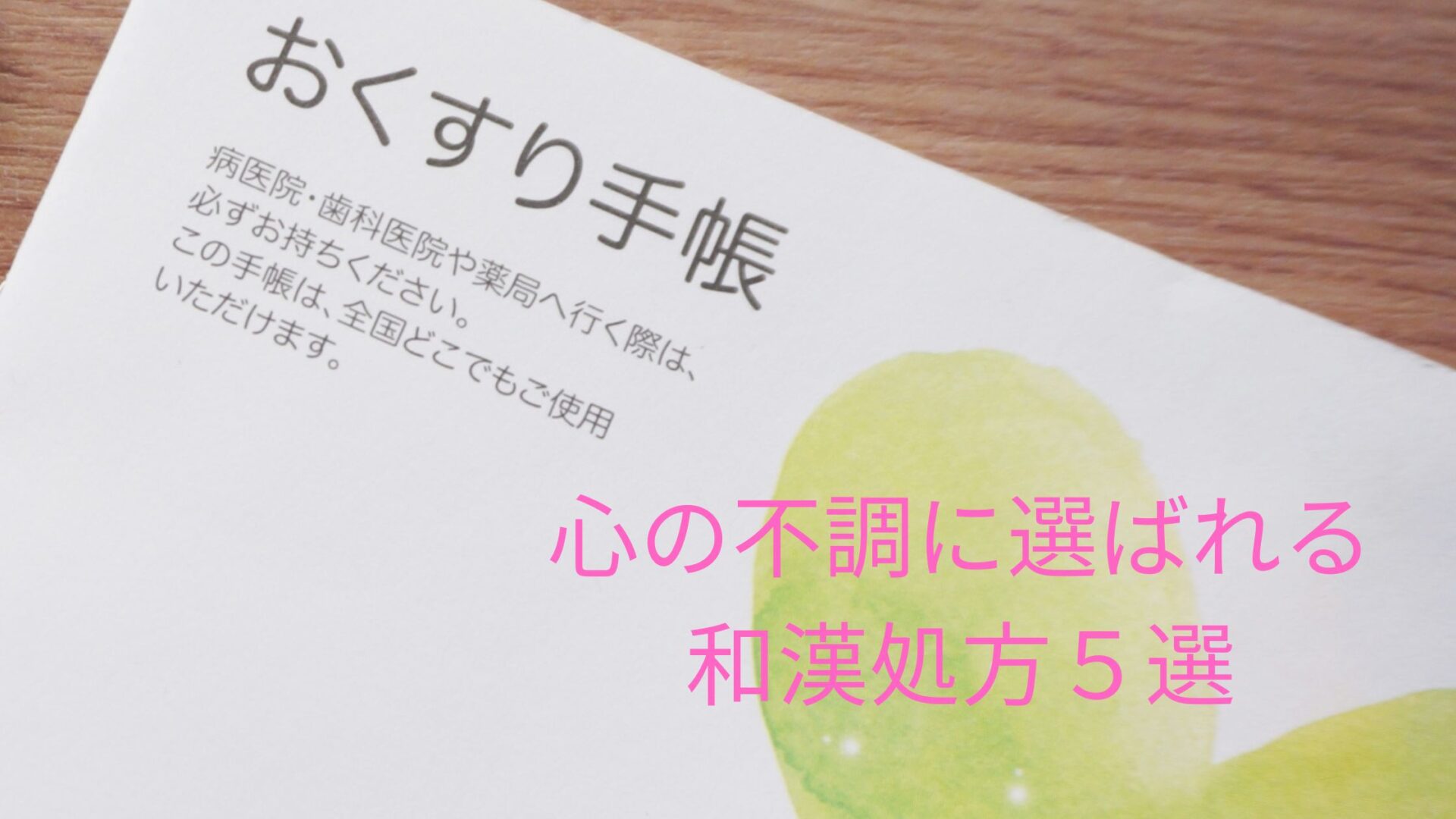
コメント