SNSやブログといったインターネットで、医薬品や健康食品・サプリメントの広告を見かけることが多くありますよね。
実は、医薬品の効能・効果、健康食品・サプリメントの広告表現は、薬機法を遵守しなければなりません。
しかし、「薬機法ってなに?」「なんだか難しそう」と思う人もいるでしょう。
そこで、今回は登録販売者ライターであり、YMAA(薬機法医療法広告遵守)個人マークを取得している筆者がやさしく解説していきます。
薬機法の基本とNG表現を知っていれば、薬機法は難しいものではありません。
ぜひ、この記事で理解を深めてくださいね!
※筆者は登録販売者資格を持ち、薬機法広告の適正表現を学んだ証であるYMAA個人マークを取得。
医薬・健康分野に特化したWebライターとして、正確で信頼性のある情報発信を心がけています。
薬機法の基本
「そもそも薬機法ってなに?」と、感じている人も多いのではないでしょうか。
ここからは、薬機法の基本情報について、やさしく解説していきます。
薬機法の正式名称は?

私たちがよく目にする「薬機法」の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
とても長いため、実務などで使う際には「薬機法」と略される場合が多いです。
そのほかに「医薬品医療機器等法」と、表現されることもあります。

薬機法って正式名称ではなかったんですね!



略称は便利ですが、正式名称もしっかり押さえておきましょうね
薬機法の目的とは?


薬機法の目的や内容を把握できるように、箇条書きで簡単にまとめました。
薬機法の施行による主な役割は、以下のとおりです。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の内容
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器・再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保する
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等製品の使用による保健衛生上の危害の発生・拡大の防止のために規制を行う
- 指定薬物の規制に関して必要な措置を講じる
- 医療上、特に必要性が高い医薬品、医療機器・再生医療等製品の研究開発の促進を図る
※上の表にある法令情報は、以下の法文検索サイトを参考に筆者が編集・要約しています。
参照:e-Gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
このブログでは、みなさんにとって一番馴染みのある「薬機法」という表現を使用していきます。



法律の名前って小難しいので「薬機法」のほうが分かりやすいです!



薬機法の目的や内容を知っておくと、正式名称も理解しやすくなりますよ
薬機法の必要性とは?


「薬機法」の目的や役割を理解することで、その必要性の把握が可能です。
ここでは、薬機法が社会全体に対して求めている点を分かりやすく解説していきます。
薬機法の必要性におけるポイントは、医薬関係者などの責務や役割が定められていることです。
どういった内容なのかを簡単にまとめてみました。
「薬機法」が定める医薬関係者等の責務・役割の内容
| 医薬品等関連事業者等の責務 | 製造販売業者や薬局開設者、医療機関などは、情報共有を通して、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保、保健衛生上の危害の発生・拡大防止に努める |
| 医薬関係者の責務 | 医師、歯科医師、薬剤師などは、医薬品等の有効性・安全性に関する知識・理解を深め、適切な利用と正確な情報提供に努める |
| 国民の役割 | 一般の人々も、医薬品等を適正に使用して、有効性・安全性に関する知識と理解を深めるように努めることが求められている |
※上記の内容は、e-Gov法文検索を参考に筆者が編集・要約しています。
参照:e-Gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
ここで押さえておく「薬機法」における必要性には、医療・医薬関係者や私たちにも役割があるという点です。
薬機法の必要性に関わる3つのポイント
- 医薬品の品質管理は「医薬品等の関連事業者」(製造販売業者など)の責務である
- 医薬関係者(医師、歯科医師、薬剤師など)は、有効性・安全性をもとに適切な利用と正確な情報を提供する
- 私たち、国民も医薬品等の有効性や安全性を理解して、適正に使用する
薬機法には、医療や医薬に関わる人だけではなく、私たちの健康と安全を守るために制定されています。



医薬品に関する法律である薬機法には「国民の役割」もあるんですね



医療関係者だけに必要とされている法律ではないことを押さえておきましょう
薬機法で注意すべきNG表現とは?
薬機法は、医療や医薬に関わる人だけでなく、私たちの健康と安全を守るために定められた法律です。
特に、インターネット広告や街頭広告において表現する際、薬機法に抵触してしまうケースも少なくありません。
ここでは、薬機法で注意すべきNG表現を紹介していきます。
「治る」「効く」「予防できる」はNG表現


薬機法に抵触してしまうNG表現の代表例として
- 「治る」
- 「効く」
- 「予防できる」
などがあります。
インターネットを利用していると、健康食品やサプリメントの広告を見かけることもあります。
しかし、これらの表現は薬機法に抵触する恐れがある「NG表現」にあたります。
NG表現となってしまう理由は、健康食品やサプリメントが「医薬品である」とみなされてしまう可能性があるからです。
健康食品やサプリメントが「医薬品」としてみなされてしまう例
- 効能効果を標榜している
- 医薬品の名称を使用している
- 用法・用量を記載している
※上記の内容は、e-Gov法文検索を参考に筆者が編集・要約しています。
参照:e-Gov法令検索|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
健康食品やサプリメントは、あくまでも食品であり、医薬品ではありません。
そのため「効く」「治る」「予防できる」といった表現を使用することで、医薬品として扱われてしまうのです。



よく見かける健康食品やサプリメントの広告は薬機法に抵触している場合もあるんですね



健康食品やサプリメントは「医薬品」ではないことを理解しておきましょう
「個人の感想です」でもNG表現になる場合
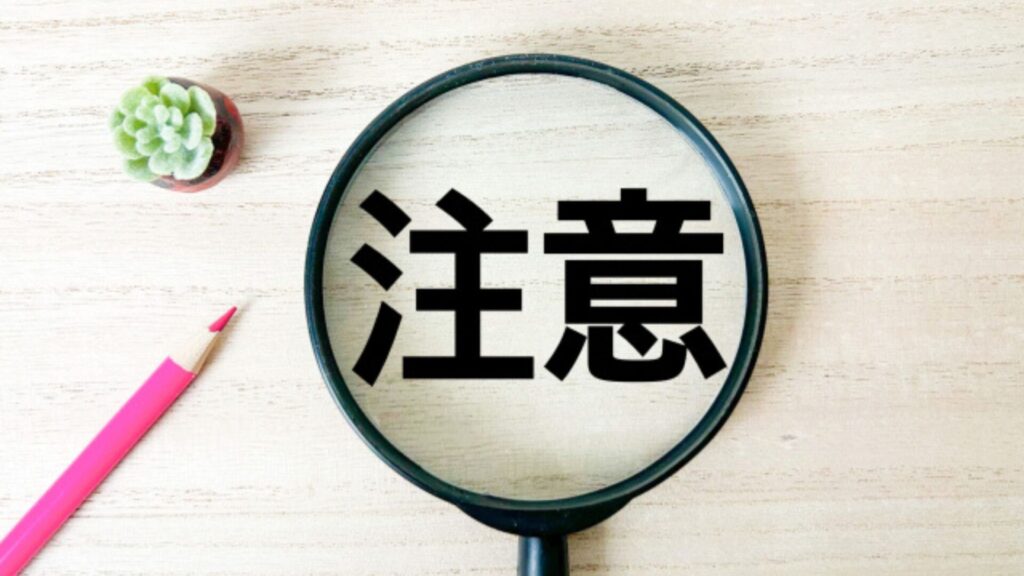
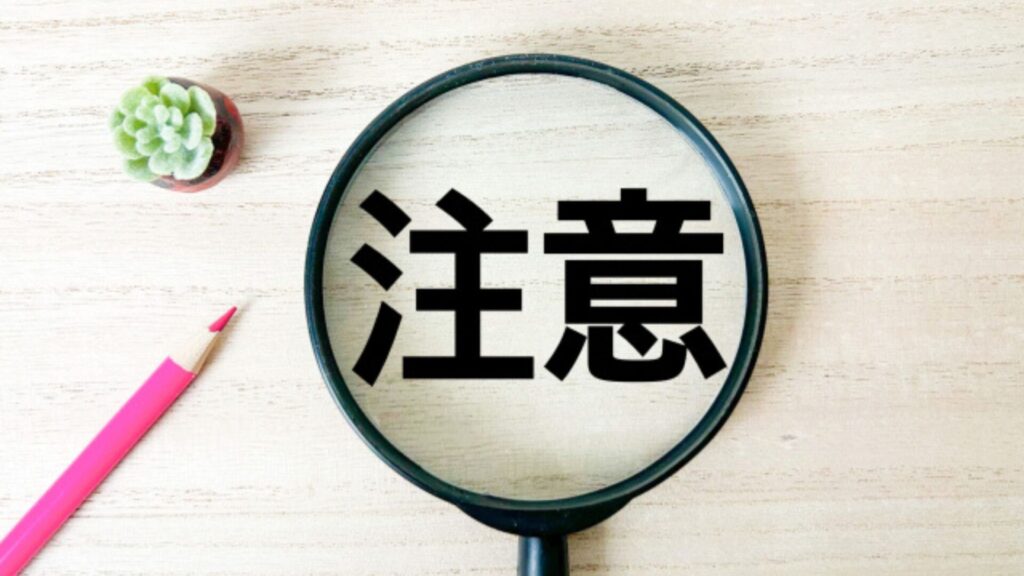
健康食品やサプリメントの広告で見かける「個人の感想です」という言葉も、NG表現になる場合があります。
薬機法の「医療法分野」において、広告での表現が禁止されているのは、次のような例です。
禁止される広告の基本的な考え方
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する内容の広告
- 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、効果に関する体験談の広告
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させる恐れがある広告
- 誤認させる恐れがある治療等の前後の写真などの広告
※上記の内容は、厚生労働省:「医薬品等の広告規制について」を参考に筆者が編集・要約しています。
参照:厚生労働省|医薬品等の広告規制について
上記の表をもとにすると、「個人の感想です」という表現がNGになる場合と、ならない場合があります。
「個人の感想です」がNG表現にあたる場合
- 対象となる病院や会社から金銭などの謝礼を受け取っている場合
- 病院や会社の経営に関与するものの家族などが「病院の利益」のために表現した場合
「個人の感想です」がNG表現にあたらない場合
- 患者等が自分の意思で、病院や商品を推薦する書籍の出版やSNSの投稿をおこなった場合
- 報酬が一切発生していない場合
※上記の内容は、e-Gov法文検索を参考に筆者が編集・要約しています。
参照:e-Gov法令検索|不当景品類及び不当表示防止法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
「個人の感想」としていても、金銭や物品などの謝礼の受け渡しが行われている広告は薬機法違反になることがあります。



広告主が利益を出すために「個人の感想です」を買い取っている場合はNGなんですね!



自分の意思で「個人の感想です」と表現するのは、原則としてNGにはなりません
NG表現にはグレーゾーンも存在する
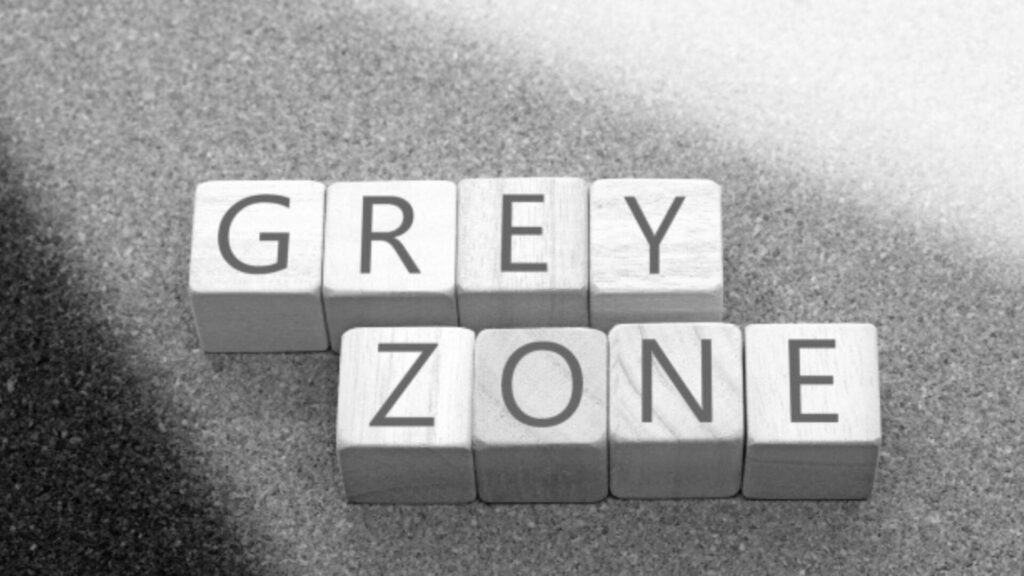
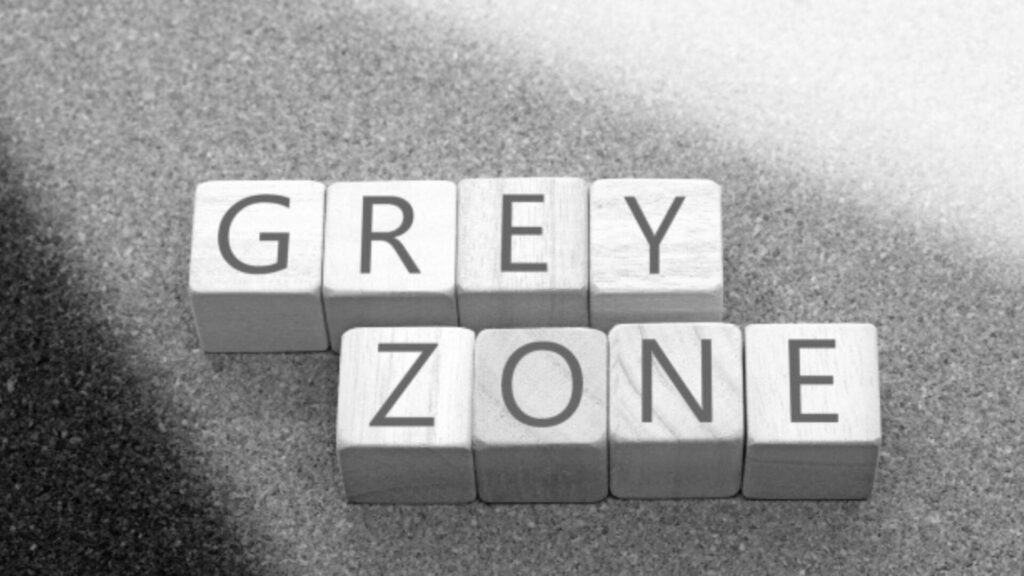
薬機法では、NGになってしまう表現とOKとされる表現の「グレーゾーン」も存在します。
薬機法に抵触するNG表現とOK表現のグレーゾーンとされる表現例
- 栄養補給や健康の維持だけにスポットを当てた表現
- 配合されている成分だけを記載する
- 特定の部位や症状、疾患を表記しない
※上記の内容は、厚生労働省:「医薬品等の広告規制について」を参考に筆者が編集・要約しています。
参照:厚生労働省|医薬品等の広告規制について
健康食品やサプリメントの摂取により、「身体を強くする」「健康を増進させる」といった表現は、薬機法に抵触します。
しかし、「栄養を補給する」「健康を維持する」といった表現は、必ずしも抵触するとは限りません。
また、配合されている成分「ビタミン」や「ミネラル」などを表記するだけであれば、薬機法に引っかからないとされています。
配合成分による効果・効能を表記した場合は、薬機法に触れてしまうので、注意しましょう。


特定の部位(例:お腹の脂肪)や症状(例:便秘)、疾患(例:ガン)に効果があるなどの記載も薬機法上、NG表現にあたります。
そのため、健康食品やサプリメントを摂取することで「治療できる」と誤解させることは禁止です。
「健康の維持のために利用ください」などの表現であれば、OKとされるので、上手に言い換えるように心がけましょう。



健康食品やサプリメントで、体を治療することはできないですもんね



薬機法に抵触する表現は、健康を損なう可能性があることを覚えておきましょう
まとめ
この記事では、薬機法の基本と注意すべきNG表現について、詳しく解説していきました。
今回の内容をまとめると、以下のとおりです。
- 薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
- 薬機法の目的には、医薬品の「品質、有効性、安全性を確保」「保健衛生上の危害の発生・拡大の防止」「指定薬物の規制」「研究開発の促進」がある
- 薬機法は「医療や医薬に関わる人だけではなく、私たちの健康と安全を守る」必要性のもと制定されている
- 「治る」「効く」「予防できる」は、薬機法に抵触してしまうNG表現
- 「個人の感想です」という表現も場合によっては、薬機法違反になる
身近なネット広告や街頭におけるチラシの中には、薬機法に抵触してしまっているものも少なくありません。
薬機法を守っているかどうかを確認することは、自分の身を守ることにも繋がります。
「自分は大丈夫」と軽く考えずに、法律を遵守することを心がけていきましょう。


日向未来
医療・健康ライター

コメント